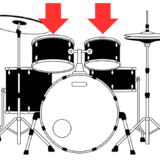同じメトロノームを見て演奏していても、なかなかタテが合わないことが多いですよね。
メンバーで如何に「テンポ感を共有できているか」「内部テンポが合っているか」で演奏の印象が大きく変わってきます。
今回は、打楽器アンサンブルがもっとまとまって聞こえる!
テンポ感・リズム感を共有する練習方法を紹介していきます!
テンポ「感」リズム「感」
テンポ感・リズム感を共有するためには、内部テンポが一致している必要があります。
速く叩けない、音が当たらないなど演奏の技術的な課題ではなく、本人の身体の中でのテンポ(拍)の取り方のことです。
内部テンポを共有するには身体の動きに集中するため、楽器を使わずに確認します。
テンポ「感」リズム「感」の違いを実感
ただメトロノームを鳴らして一緒に演奏するだけでは解決しないのがこの「テンポ感」「リズム感」。
「感」の違いって何?という方は、まず実際に体感してみましょう!
以下のの2つを時計の秒針に合わせてたたいてみてください。
(メトロノームなら「60」にしましょう)

2.赤ちゃんを寝かしつけるようにやさしく、2秒おきに手をたたく

どちらも同じ「四分音符=60」を刻んでいますが、ずいぶんと雰囲気が違いませんか?
ザックリ言うと、テンポ感やリズム感というのは、同じテンポの中でのスピード感や勢い、強さの感覚のことです。
身体を使って、体感していく
相手と向かい合って、「せっせっせーのよいよいよい♪」など手遊びしたことはありませんか?
同じ歌を歌い、お互いの手を合わせてたたく動作を繰り返していると、自然と「内部テンポが共有」されます。
拍子感を持った演奏、リズミカルな演奏、または前へ進んでいく演奏のためには、
基準となる「テンポ(拍)」と自分が実際演奏している「リズム」両方を同時進行で感じていなければなりません。
身体を動かしてテンポ(拍)を感じたりリズムを刻むトレーニングは、ダルクローズ、コダーイ、オルフなどによる音楽教育メソードやリトミックの手法として世界的に活用されています。
「リトミック」と聴くと幼児教育をイメージされがちですが、実は子どもから大人まで充分活用できる手法です。
演奏に一体感が生まれる
テンポ感が共有されていれば、たとえ何かがズレてしまっても音楽的なまとまりをもった演奏になります。
音楽は「時間」であり、「時間」つまりは「テンポ・拍」が存在してこそ進んでいきます。
まずはテンポ感を共有しているだけでも、一体感のあるアンサンブルになります。
同じタイミング・スピード感で足を出さなければならない「2人3脚」や息の合ったダンスなどは、内部テンポの一致が目に見える結果として出ていますね!
内部テンポを共有する練習方法
まずは楽器を使わず、お互いに身体を動かして、共有していきます。
メトロノームを付けていれば安定した正確なテンポをつかめます。
メトロノームを付けないでやれば、アゴーギクやリタルダンドなどのテンポ変化も自然と共有できると思います。
音源を流しながらやってみるのもおすすめです。
目的に応じて使い分けてみてください。
【アゴ―ギク】…テンポの揺らぎ、伸び縮み。
方法1 お互いの肩でテンポをとりながら歌う

隣の人の肩をテンポでたたきながら、自分のパートを歌います。
円形になれば、全員でテンポをたたき合うことができ、さらなる一体感が生まれると思います。
2人組になって1人は楽器で演奏、もう1人が演奏している人の肩をたたく方法もあります。
誰からも叩かれない端っこの人はリーダーや先輩にするとよいでしょう。
方法2 ハイタッチ

例えばキメのリズムを取り出して2人組でハイタッチをする、複数人で円になって拍をハイタッチします。
ただ「たたかれるだけ」にならないように、お互い同じ力加減とスピード感で叩くことが重要です。
(初心者の場合は「たたかれるだけ」の練習になってしまっても効果的です。相手のリズムを身体で受け取るだけでも感覚を掴むことに繋がります。)
ハイタッチでテンポを取りながら自分のパートを歌うのも効果的です。
基礎練習でやっているチェンジアップを両手ハイタッチしてみるのもおすすめです。
また、2人組で鏡合わせのようになり、十六分音符をハイタッチで叩く練習も効果的です。
(片方の人は左手スタート、もう片方の人は右手スタートで手順は逆になります)
開始時の「せーのっ」「さん、はい」など呼吸を大切にして、最初から合うようにしましょう!
バネ(弾力)が重要

基本的に「大縄跳びの縄を回す感覚」「ボールをドリブルする感覚」で拍をとります。(ゆったりとした穏やかな曲であればまた違ってきますが。)
テンポ感を共有練習をする時は、お互い同じ力加減になるようにします。
「何だか違うな?」と思ったら、お互い指摘し合ってすり合わせていきましょう!
曲の雰囲気によって、同じリズムでも くっついている時間や跳ね方が変わってきます。
ひた、ひた、とリズムを取ると良いかもしれませんし、
緊張感の高い場面なら素早い動作になるかもしれません。
重々しいのか?軽やかなのか?イメージを共有していくことが大切です。
テンポをとりながら歌うと合っているのに、楽器で演奏すると合わない場合は「リズムは理解しているけど、楽器の奏法でつまづいている」可能性が高いです。楽器を使わないリズムの練習は、うまくいかない原因の特定にも活用できておすすめです。
まとめ
以上、テンポ感・リズム感を共有する練習方法でした!
メトロノームをつけているのに何だか合わないな?という時は是非試してみてください。
繰り返すうちにアンサンブルに一体感が出てくるはずです!
それでは、また!
部活指導やレッスンで活用できる
”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!
「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪
詳細・参加申込はこちら